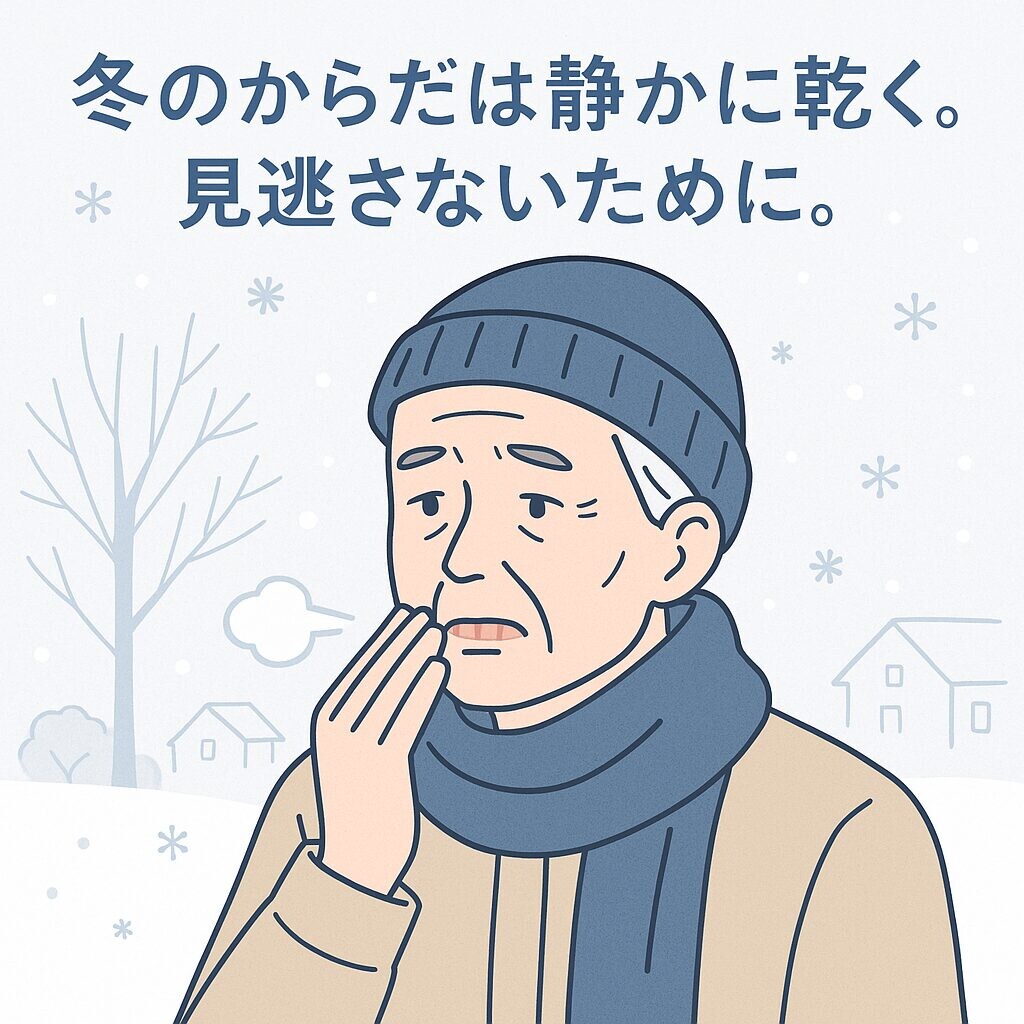-

ヒートショック、脱水にも注意!
乾燥による脱水は、血液を濃い状態に! ■冬の脱水を防ぐための対策 冬場は空気が乾燥し、気温も低いため、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高める脱水状態になりやすくなりま… -



循環器系に深刻な影響が・・・
冬は寒さによる血管収縮や脱水で血圧が変動しやすく、特に朝晩や暖かい部屋から寒い場所への移動(ヒートショック)で血圧が急上昇し心臓に負担をかけ、脳卒中や心筋梗… -


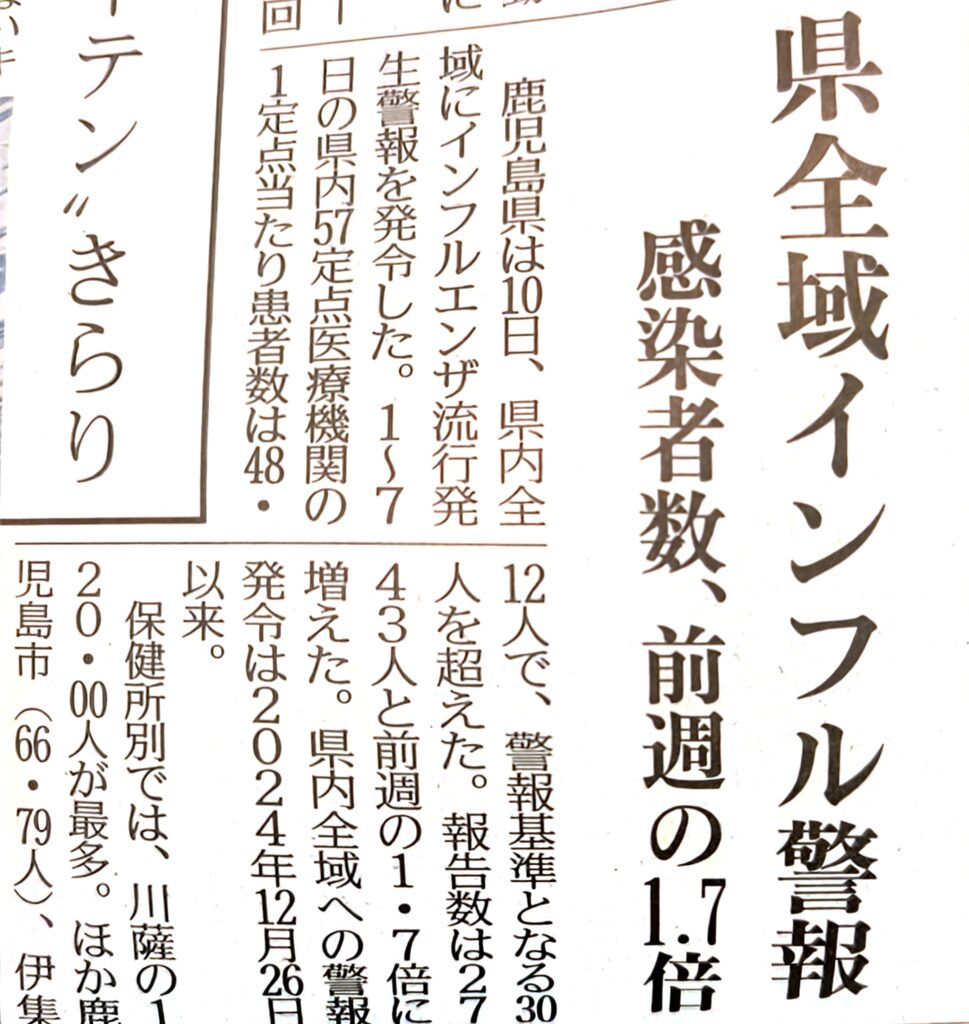
インフルエンザ流行発生警報
鹿児島県は10日、県内全域にインフルエンザ流行発生警報を発令しました。 風邪やインフルエンザなどのウイルスは1日で100万倍も増殖するといわれています。人間は免疫シ… -



12月〜3月が流行シーズンです!
■インフルエンザと普通の風邪との違い 一般的に、風邪は様々なウイルスによって起こり、のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状が中心で、全身症状はあまり見られませ… -



巡りをととのえましょう
■巡りを整えるための具体的な対策 血液の巡りを良くし、冷えにくい体を作るためには、日常生活の中で以下の点を意識することが効果的です。 1. 体を温める「食事」の工… -



『生姜酵素』作ってみませんか?
■生姜酵素の主な効果 ① 体を温める(冷え対策) 生姜に含まれる ジンゲロール や ショウガオール は血流を良くして、体をポカポカにしやすい成分です♨️ 酵素により発酵… -



あなたの冷えは・・・
■冷えの主な原因は、体が深部体温を維持するために手足への血流を減らすことです。この血流の低下は、体内のエネルギー生産が不十分で代謝が悪くなることや、運動不足、… -



飲む【美容液】
福山雅治さんが愛用している【飲む美容液・瓊玉膏】 には、こんな働きが‼️ 【主な効果・働き】 ① 疲れやすい・体力低下の改善 ・虚弱体質 ・慢性疲労 ・病後・産後の回… -



逆流性食道炎
逆流性食道炎とは、胃の内容物(胃酸を含む)が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症が起きる病気です。食道には胃酸から守る防御機能がほとんどないため、胃酸に繰…
-


腸を整えてストレス緩和
「腸」を整えてストレスコントロール! “脳腸相関”についてご存じですか? 脳と腸は自律神経系、内分泌系、免疫系の三つの経路を介して、互いに影響を及ぼしあっており、これを 「脳腸相関」といいます。 ☆不安定な気分を安定させ、心を穏やかにする役割を... -


乾燥&マスクかぶれに!
コロナ禍で長時間マスクを着用することにより、肌トラブルの人が増えています。 冬は空気が乾燥し、肌トラブルが起きやすい季節です。気温が下がり血流が低下すると、皮脂腺や汗腺の働きが低下し、皮脂の分泌が抑制されてしまいます。 ◎夏は体を冷やすため... -


冬の血圧変動に注意!
皆さま、寒い日が続いていますが、いかがお過ごしですか? 冬場の血圧変動に注意しましょう❗️ ◯寒くなると、体温を逃さないように、血管が収縮し、血圧が上昇します。 ◯ヒートショックと呼ばれる脱衣所と浴室の温度差が血圧変動の要因になります。 ◯冬は... -


免疫を落とすのを防ぐ!
☆免疫を上げる前に免疫を落とすのを防ぐ! 『新型コロナウイルス対策で、どのように免疫力を上げればいいですか?』という質問がよくあります。 免疫力を上げるためにいろいろなものを飲むのはいいのですが… 免疫力を落とさない!ことも大事かと思います。... -


フェイスシールド!
☆フェイスシールドで防ぐ 店頭で使用していますが、呼吸しやすく快適です。 特にマッサージ中の時は、息苦しくありません。 ◎メガネタイプなので、ズレない。 ◎飛沫防止に。 ◎呼吸しやすい。 ◎メガネをしていても、曇らない。 ◎軽量。 ◎男女兼用。 1枚 5... -


100%国産 熟成黒にんにく🧄
しばらくの間、品切れしていました 熟成黒にんにくが入荷しました! 🧄100%国産(奄美・笠沙) 🧄自然発酵だから無添加・無農薬栽培 🧄甘いフルーティーな味で美味しい 🧄ニオイが気にならない 🧄疲労回復や体力増強に❗️ 80g 1080円(税込) くそ暑い夏を乗... -


むずむず脚症候群に、リンパマッサージ!
むずむず脚症候群は、レストレスレッグス症候群(舌かみそ〜う)と称され、睡眠障害の要因です。 ◎むずむずする ◎ほてる ◎虫がはうような感じ ◎電気が流れている感じ ◎ピクピクする ◎脚を動かしたくなる など、夕方から夜にかけて症状が出るのが特徴ですが... -


あれ?ここのシミ・・・あったかな??
シミの原因は、7割が紫外線で残りの3割のうちの大部分を肝臓の機能低下が占めるとも言われています。 肌の外側ではあかとして出るように、肌の内側にも古くなった細胞などの老廃物は出てきます。その老廃物は身体の中のゴミ掃除屋さん(マクロファージ)がき... -


紫外線が強い!日差しに注意!
日差しを浴びると、紫外線から肌を守るために活性酸素が発生します。 活性酸素は眼には見えませんが、身体を作る一つ一つの細胞の遺伝子に傷をつけてしまいます。 海水浴やバーベキュー、運動会など長時間日差しを浴び続けると、肌が赤くなったり、ほてり... -


夏に増える、こむら返りを防ぐ!
「こむら」はふくらはぎを指し、この部分の筋肉が過剰に収縮したまま動かせなくなった状態がこむら返りです。 激しい運動中や、睡眠中に起こることが多い。 筋肉の線維の中には、伸びすぎたり縮みすぎたりするのを防ぐセンサーがあり、この働きがおかしく...